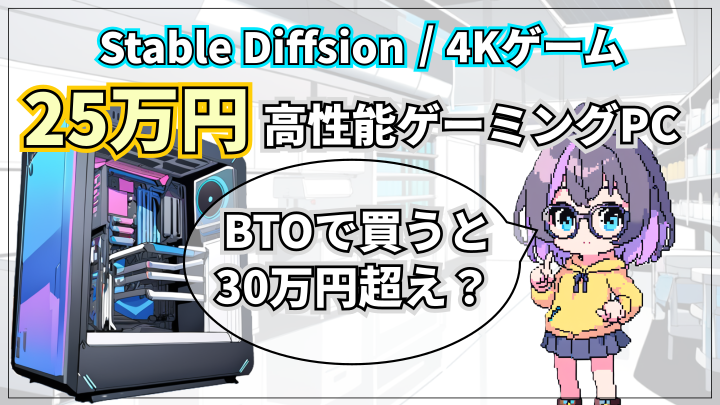【自作パソコン】パーツの選び方のすべて!筆者使用PCを例に解説【Core Ultra 9+RTX5070】

この記事では筆者が使用しているパソコンの紹介と、パソコンを作るときのパーツの選び方を紹介します。

白パーツで統一して組みました。

PCパーツ構成
| パーツ | 詳細 |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 9 285k |
| GPU | GeForce RTX 5070 (GIGABYTE) |
| マザーボード | ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI |
| メモリ(DRAM) | G.Skill DDR5-5200 48GB x4 |
| CPUクーラー | DEEPCOOL LT360 WH ARGB |
| SSD | Western Digital WD BLACK M.2 SSD 4TB x2 |
| HDD | Western Digital WD Blue HDD 8TB |
| 電源 | NZXT C1000 1000W |
| ケース | Thermaltake The Tower 600 Snow |

メモリを積めるだけ積んでみました。驚異の192GB!
私のパソコンの用途
このパソコンを組む時に考えていた用途は以下の通りです。
- ゲーム
- クリエイティブ用途(3DCG, 動画編集など)
- 科学計算
- Stable Diffusionなどの生成AI
パーツの選び方
ケース

まずはケースから選びました。ケースを自由に選べるのは自作PCの醍醐味だと思います。
見た目以外に、ケース選びの注意点は次の通りです。
- 【向きの制約】デスクの右側にPCを置く想定のケースが多い
- 【ケースの大きさ制約】設置予定場所に置けるか
- 【内部の大きさ制約】入れたいパーツ(特にCPUクーラーとGPU)が搭載できるか
まず向きの制約ですが、PCケースはケース右側にマザーボードを設置する関係ケース左側が透けているものが多いです。
そのため、デスクに対して右側にPCを置くことにしたほうがケースの選択肢が広がります。
ケースの大きさ制約については、欲しいケースの寸法を調べて実際におけるかはどうかを確認しておいたほうが良いです。
写真で見るより実物は大きく感じるので、数字で確認しておいたほうが安全です。
内部の大きさ制約については、搭載したいパーツが物理的に入るかはできる限り調べておいたほうが良いです。
最低限以下の点に注意しましょう。
- マザーボードのサイズ(ATXサイズなど)に合うケース、またはそれよりも大きいケースかどうか
- CPUクーラーは高さ的に入るかどうか
- 入れたいGPUは長さ的に入るかどうか

このあたりはミスったときのダメージがでかいので注意です。
えりるさんは部屋の制約からケースをデスク左側に置かなくてはいけなかったのでかなり選択肢が狭まりました。
左でも置けるケースの中で見た目重視で選びつくした結果、Thermaltake The Tower 600 Snowになりました。
かなり大きいケースですが、PCパーツを見せることにこだわったケースで、かなりカッコいです。
しかしながら、上部のI/O部分がかなり窮屈で、ケーブルが柔軟なものでないとHDMIケーブルとかが配線しにくかったです。
(ファンにケーブルが干渉する!)
でもまあ、それを許せるくらいの見た目の良さだと思います。
ケーブルは柔らかくて細いものを用意するようにすれば大丈夫なので、おすすめです!

レビュー記事は準備中です。しばらくお待ちください。
CPU
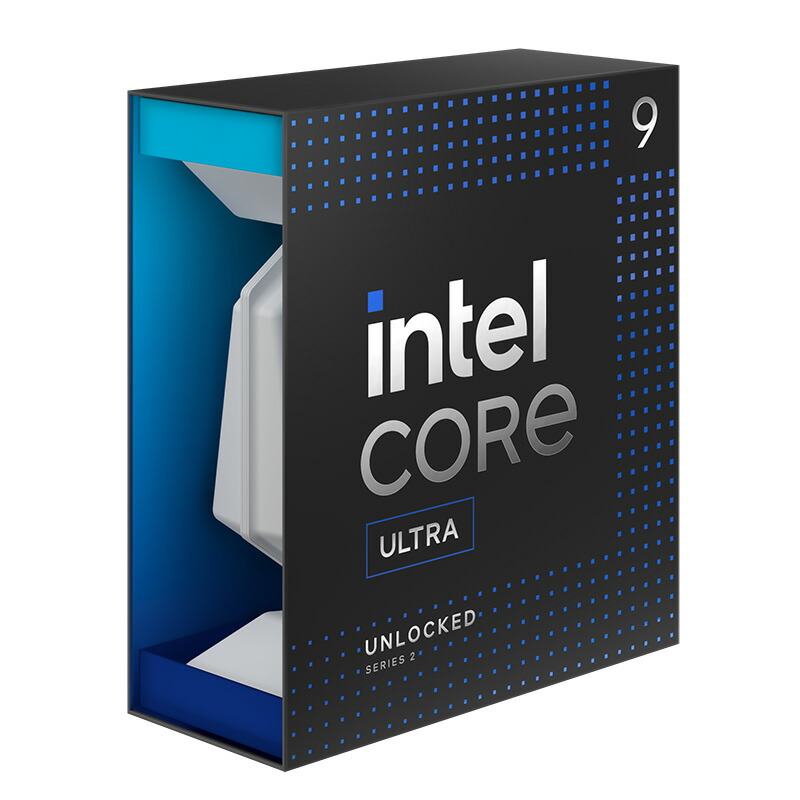
CPUはIntelの最新・最上位CPUのCore Ultra 9 285K にしました。
24コア、24スレッドのCPUでコア数が多いのが魅力的ですね。
ハイパースレッディングがないのが残念ですが、動作もサクサクで文句はありません。
用途としては以下を考えて選びました。
- クリエイティブ用途で使えてソフトウェアの動作が安定していること。
→ 信頼性重視 - 4Kゲーミングに耐えうること。
→ 最上位クラスのCPU - 科学計算用途で使用できること。
→ シングルスレッドの処理能力が高い & 物理コア数が多いこと。
1と2だけだったらRyzen 9 9950X3Dかなあという気になるのですが、3の科学計算をブログで扱いたいんですよね。
科学計算で並列計算をするときは物理コア数分だけスレッドを立てて計算した方がパフォーマンスが良いそうです。
(参考: https://jp.mathworks.com/matlabcentral/answers/2174537-parallel-computing-toolbox-matlab)
これがコア数の多いIntelを選択した決め手ですね。
正直Core Ultra 7 265Kで十分だったんですが、最上位を所有したい欲に負けました。
コスパ的には265Kが圧倒的に良いです。
グラフィックボード(GPU)
GPUはGIGABYTE製の RTX 5070 にしました。
ほんとはRTX5070Ti または RTX5080が欲しかったんですけど買えなかったんです…。
RTX5070は割と売ってるみたいですね。Amazonで調べると「Amazon.co.jp」が販売・発送する商品が割とありました。
以下のリンクからRTX5070の検索に飛べるので良ければ確認してみてください。
用途としては以下を考えていました。
- 4Kゲーミングができる。(60 fps位出れば私は満足)
- Windows で Stable Diffusion を使った画像生成ができる
→ ビデオメモリ(VRAM)多め, 並列計算能力重視
1の4Kゲームをやろうと思うとRTX5070Ti以上かRADEON RX9070くらいは欲しくなると思います。
2のStable DiffusionもやりたかったのでNVIDIA GPUにしました。
そしてRTX5070Ti & 5080の争奪戦に無事敗北し、何とか手に入れられたのがRTX 5070でした。
でも、いざ使ってみるとRTX50シリーズのDLSS(NVIDIAのフレーム生成技術)がすごいのか、
Monster Hunter Wildsを4K 高品質設定で60 fps位出ます。
ゲーム用途は満足できる性能でした。
12~13万円で4K 60fpsでゲームができると考えれば悪くはない…かな?

しかしここで悲劇が起きます。
2つめにやりたかったStable Diffusionが動作しないんですね。(RTX50シリーズは非対応)
なので、いろいろやり方を調べたり試したりしながら試行錯誤。
その研究結果が以下の記事になりました。
この辺は日本語の情報が皆無で、特にxformersの導入あたりの日本語情報はえりる研究室だけなんじゃないかな。
少なくとも一番早いレベルの日本語記事だったと思います(えりる研究室調べ)。
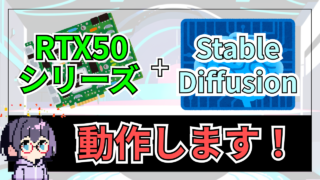
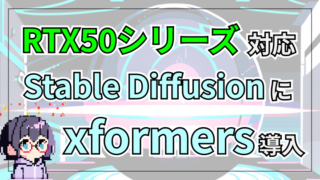
ここまでやるならRADEONでもよかった説がありますね。

「RADEONでStableDiffusionを動かしてみた!」
とかもやろうかな。予算次第なところはあるけど。(小声)
マザーボード

マザボはASUSのTUF GAMING Z890-PRO WIFIにしました。重視した点は以下の通り
- 白!(最重要)
- Z890チップセット(285Kを運用するので念のため最上位)
で選ばれたのがTUF GAMING Z890-PRO WIFIでした。
ASUSはソフトウェアまわりも優れているのが良いと思って選びましたが、
ROGは高すぎるのでコスパで選んでTUF。

廉価版を選んだ結果かはわかりませんが、悲劇へと繋がります
Core Ultra 9 285Kの動作クロックが5.5GHz以上に上がらないんですね。
Intelの285Kのページ によると5.7 GHzまでいくらしいんですけどね。
ROGだったら5.7 GHzまで上がったのかなあとか思いながらも、
違うかもしれないので現在調査中。
でもデザインはメカメカしくて気に入っています!
CPUクーラー

CPUクーラーは簡易水冷のDEEPCOOL LT360 WH ARGBにしました。
CPUクーラーに求めたことは以下の3つ。
- 285K(またはRyzen 9 9950X3D)をぶん回したときに冷やしきれること。
- メモリやマザーボードのヒートシンクなどと干渉しないこと。
- 白いこと!
最初は空冷にしようとしてました。水冷クーラーは捨てにくいですからね。
白い空冷だと以下のDEEPCOOLのAK620が最強でしょうか。

このクーラー自体の対応TDP(Thermal Design Power)は情報がないですが、
これの前モデルはTDP260 W対応なのでこれも260Wくらいはいけるでしょう。
カタログスペックではCore Ultra 9 285K(TDP 250 W)もいけそうです。
ですが、すごく大きいのでケースに入れたときにメモリやらケーブルやらが干渉しないか不安でした。
The Tower 600 は結構特殊なケースなので、悲劇が待っていそうです。

実際、空冷にしていたら電源ケーブルが干渉していたと思います。
なので、水冷で行くことにしました。
PCケースのThe Tower 600 は420 mmのラジエーターまで入るらしいのですが、
ちょっと余裕をみて360 mmサイズのラジエーターにすることに。
ギリギリ攻めて変なところ干渉して入らないとかになったら最悪ですからね。
DEEPCOOLのTDPリストで360 mmラジエータのCPUクーラーのTDPを見てみると300 Wとか書いてあったので、360 mmでいけると判断しました。

科学計算用途でぶん回しても大丈夫そうです。
簡易水冷クーラーって寿命が短いらしいんですが、DEEPCOOLのLT360の紹介ページによると、独自の水漏れ防止技術(特許取得)で寿命を延ばしているらしいです。
これを信じてDEEPCOOL LT360 WH ARGBにしました。

めちゃくちゃよく冷えます。
Core Ultra 9 285Kをぶん回しても70℃くらいでした。
メモリ

メモリはG.Skill DDR5-5200 48GB を4枚で192 GBにしました。
(DDR5は4枚さすと性能低下することがあるので非推奨なんですけどね)
メモリを選ぶときに求めたことは以下の3つ!
- メモリ動作速度よりも容量重視→ 科学計算などで使用する
- 動作速度よりも価格重視
- 白いメモリ!
メモリ動作速度(DDR5-5200だったら5200 MHz)が高いものを選んでも、価格の割に性能向上はあまりしないそうです。
以下の外部記事を参考にしました。
ちもろぐさん: DDR5メモリのオーバークロックに意味ある?【4800 vs 6000 vs 7800で検証】
メモリ動作速度は犠牲にして、その分容量に予算を使うことにしました。
現実的な値段で入手できるメモリの中で最大サイズが1枚あたり48 GBです。
その中で白くて一番安いやつを選んだ結果、G.Skill DDR5-5200 48GBになりました。

メモリ積みまくりロマン重視戦略が悲劇へと繋がります。
DDR5メモリの4枚刺しで動作させてみると、最初は5200MHzで動きました。
それで安心して、マザーボードのBIOSアップデートをしたんですよね。
じゃあ動かなくなってクロックダウン。DDR5-4400 MHzになりました。
ただ、動作速度は下がりましたが、性能低下はあまり感じないです。

でも、気分はよくない!笑
ストレージ(SSD)

SSDはM.2タイプでWestern Digital WD BLACK M.2 SSD SN850X 4TB を2つ搭載しました。
SSDに求めたことは以下の4つ!
- M.2 SSD
- 信頼性の高いメーカー
- 4TB以上の大容量
- DRAMキャッシュ付き
SSDの選び方のポイントは以下の記事に詳しくまとめました。
選び方の詳細は以下の記事に任せて、ここではざっくり説明します。
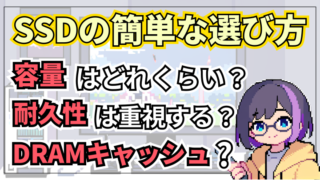
まず1つめ。
SSDにはSATAとM.2の2つのタイプがありますが、M.2タイプを選択しました。
これは単純で、M.2のほうが性能が高くてコンパクトだからです。
2つめの信頼性。えりる研究室おすすめの信頼性高メーカーは下の7つですね。
- キオクシア(元 東芝)
- Western Digital または SanDisk
- Crucial
- SK hynix または Solidigm
- SAMSUNG
この辺のメーカーだったらどれ買っても良いんじゃないかなと思っています。
選んでいたときにAmazonのセールをしていたWestern Digitalを選択しました。
3つめの容量は最低でも1TBは欲しいですね。できれば2 TBくらいあると必要十分と思います。
えりるさんは
- ゲームしたい!
- 3DCGとかクリエイティブなこともしたい!
- 科学計算したい!
とかいう用途もりもり仕様だったので、余裕をみて4 TBのSSDにしました。
ソフトウェアや素材のデータ量多くなりそうでしたし。
4つ目のDRAMキャッシュは、簡単に言うと
「DRAMキャッシュがあると性能が高いけど価格が高い」
です。
えりるさんは動画ファイルなどの大きなファイルを扱うことが多いので性能重視でDRAMキャッシュ付きのSSDにしました。
しかし、ここでちょっとポイントがあって、
SSDの性能指標でよく書かれている読み書き速度
≒ 大きいファイルを読み書きするときの速度
です。
日常的には小さいファイルの読み書きが多いので、よく書かれている読み書き速度が速いものを使っても大きなファイルを扱わない限りは体感性能はあまり変わらないと思います。
この4つをみたすSSDを探していたところ、Amazonのセールで4万円くらいになっていた
Western Digital WD BLACK M.2 SSD 4TB にしました。
えりるさんが買ったころはセールなしだと5万円超えてたのでかなりお買い得だったんですが、
今は素で4万円ですね。
ここからセールになれば3万円台に入りそうなのでねらい目だと思います。
ストレージ(HDD)
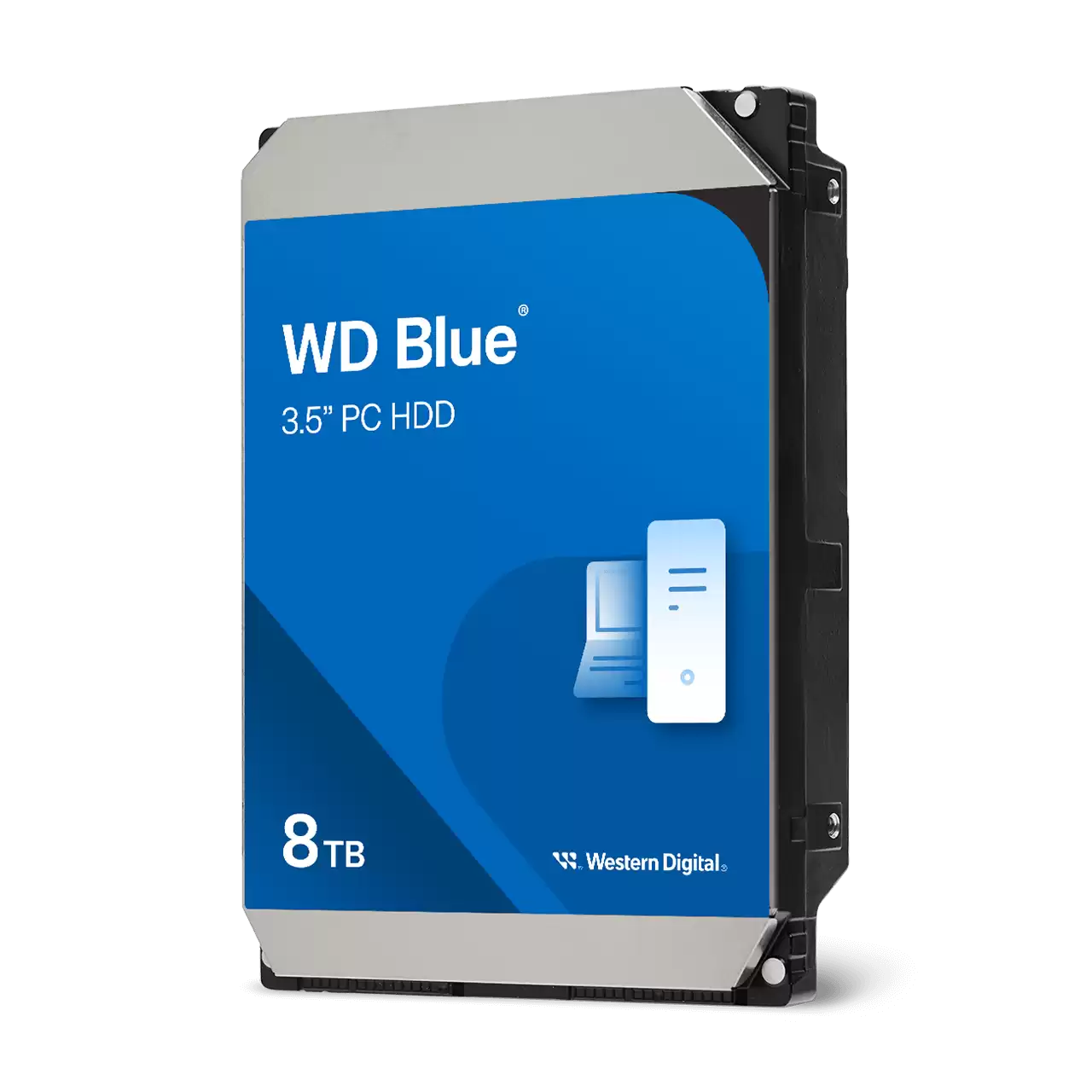
HDDはWestern Digital WD Blue HDD 8TB にしました。
HDDを選ぶときに重視したポイントは以下の通りです。
- 信頼性
- 1TBあたりの価格
信頼性については以下のメーカー製を選んでおけばよいと思います。
- 東芝(日本)
- Western Digital (アメリカ)
- Seagate (アメリカ)
あとはそれぞれ1 TBあたりの価格に直して一番コスパの良いものを選びました。
電源
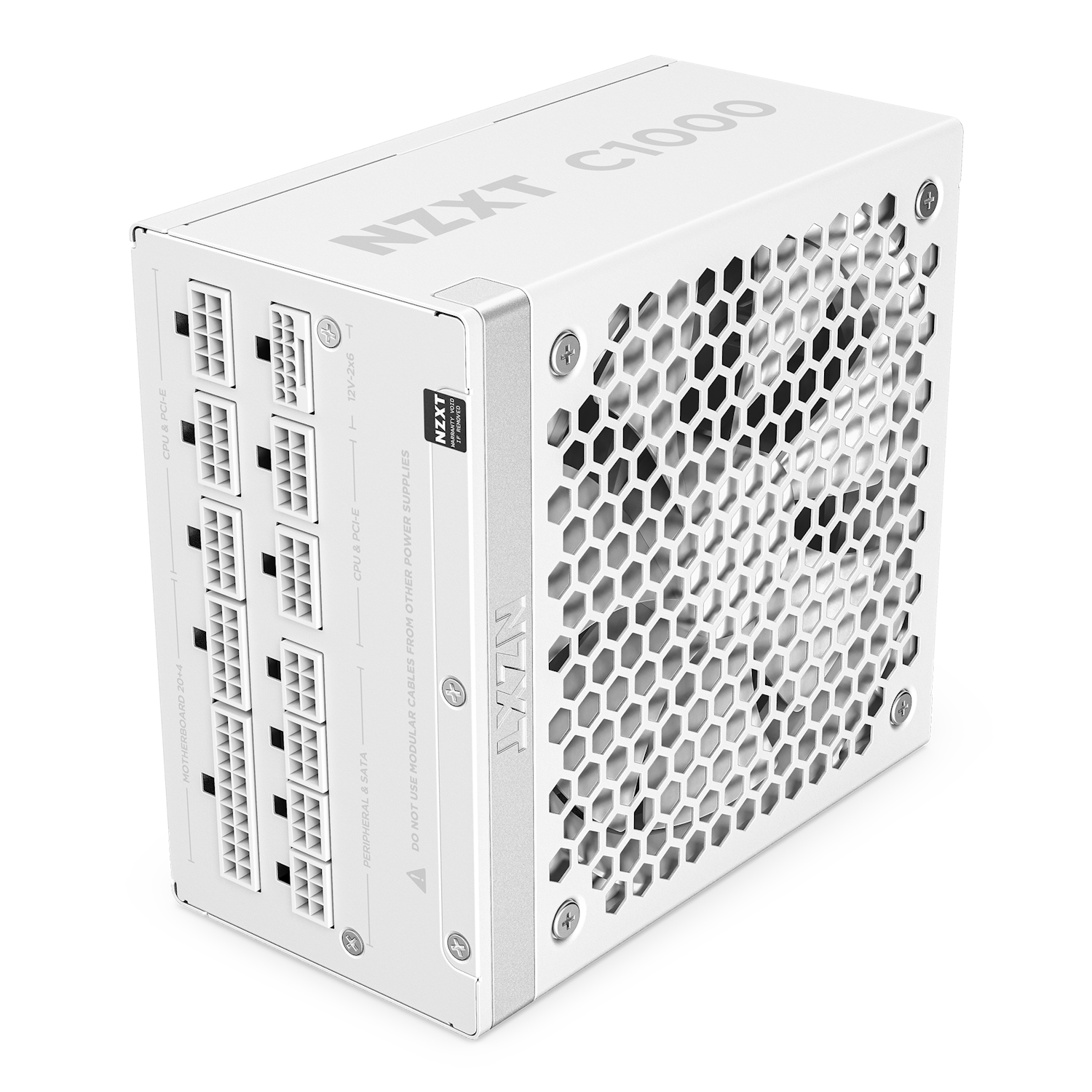
電源は NZXT C1000 という1000W電源にしました。
選定理由は、
- 聞いたことあるメーカーであること。
- Core Ultra 9 285K + RTX5080に電力供給できること
- 白くてカッコいいこと
でした。
ます、メーカーについてです。私自身特にこだわりはないのですが、聞いたことあるメーカーであることはかなり重要だと思っています。
電源って数百ワットくらいの電力が流れるので、信頼性が低いと下手したら燃えます。
なので、怪しい電源は買わないようにしたほうが良いと思います。
続いて容量ですが、最初はRTX5080を前提に選んだので過剰スペックになっています。
285Kは定格で250 W消費します。
RTX5080の消費電力は360 Wですが、要求としては850 Wを供給できる電源であることとなっています。
単純に行くと850 Wでよいとは思いますが、最低要求値というのも余裕がないなと思い1000 Wにしました。
1000 Wにしたもう一つの理由として、GPU二枚刺して Stable Diffusionを動かしてみたいなっていう淡い期待もあったからです。
1000 Wの白電源ってかなり高額なんですが、NZXT C1000は28000円で一番安かったです。
まとめ
えりるさんが使用しているPCを例にパーツの選び方を全部解説してみました。
超大作になってしまったので、ここまでたどり着いてくれた方がいらっしゃるか不安ですが、
読んでいただいてありがとうございました。
ぜひPCパーツ選びの参考にしてみてくださいね。